
※この記事にはプロモーションが含まれます。
こんにちは。スニーカー完全ガイド、運営者の「M」です。
ドクターマーチンを買ってワクワクしながら中を覗いたら、「あれ?中敷きが半分しかない…」って驚いたこと、ありませんか。
初めて見ると「これって不良品?もしかして偽物?」なんて、ちょっと不安になっちゃいますよね。私も最初、8ホールブーツでこれを見た時は「え、まさか…」と一瞬焦ったのを覚えています。ドクターマーチンの中敷きが半分のこの仕様、実はちゃんとした理由があるんです。
でも、理由がわかっても、実際に履いてみると「ハーフインソールの段差が足裏に当たる…」「かかとが痛い」と感じたり、「ハーフサイズがないから、サイズ調整はどうすればいいの?」っていう新しい悩みが出てくるかもしれません。元の中敷きの外し方や、交換すべきかどうかも気になりますよね。
この記事では、なぜ中敷きが半分なのかという理由を深掘りしつつ、中敷きの交換や外し方のヒント、そして快適に履くための具体的な対処法まで、ドクターマーチンの中敷きに関する疑問をスッキリ解決していこうと思います。

- 中敷きが半分になっている本当の理由
- ハーフインソールで起こりがちな問題点
- 悩み別(靴擦れ・サイズ感)の具体的な対処法
- おすすめの純正・市販インソールと選び方
ドクターマーチンの中敷きが半分の理由

まずは、多くの人が「え?」って思う、あの中敷きが半分しかない問題。
これ、本当に不良品でも手抜きでもないんですよ。むしろ、ドクターマーチンのこだわりや、伝統的な靴の作り方が深く関係しているみたいです。
なんでわざわざ全面じゃないのか、その理由を一緒に見ていきましょう。
ハーフインソールは偽物?

いきなり結論から言っちゃいますが、中敷きが半分だからといって偽物、というわけでは全くありません!
これは私も昔、ネットの情報で「中敷きが途中で切れてるのは偽物の特徴」みたいな書き込みを見て「そうなの!?」って焦ったことがあるんですけど、実際は違いました。
これは完全に都市伝説というか、誤解が広まったものかなと思います。
ドクターマーチンの愛用者さんの間でも「私の本物マーチンも半分だよ」っていうのは有名な話で、正規品でもごく当たり前に採用されている仕様なんです。
特にクラシックなモデルやイングランド製のものなど、特定のラインナップで見られることが多いですね。
なので、お店や通販で買って「半分だ!」ってなっても、そこだけで偽物と判断するのは早すぎます。まずは安心して大丈夫かなと思います。
もちろん、偽物が存在しないわけではありません。
ただ、判断基準は中敷きの形状以外の部分、例えばイエローステッチの縫い目の粗さ、ソール側面の刻印(”The Original”など)の鮮明さ、ヒールループのロゴの織り方などで総合的に見る必要があります。
とはいえ、最近はそこも精巧になっているので、やはり正規店での購入が一番安心ですね。
中敷きが半分なのは伝統的な構造

じゃあ、なんで半分なのかっていう一番の理由がこれ。「伝統的な靴の構造」に倣(なら)ってるから、みたいですね。
ドクターマーチンのクラシックなモデルって、「グッドイヤーウェルト製法」っていうすごく頑丈な作り方をしてるんです。
これは高級な紳士靴や本格的なワークブーツにも使われる製法で、アッパー(甲革)とソール(靴底)が直接縫い付けられていないのが特徴です。
だからソール交換も可能で、長く履けるんですね。
こういう本格的な革靴やブーツだと、もともと靴本体にしっかりしたインソール(「フットベッド」とか「中底」って呼ばれます)が組み込まれているんです。
そういう靴って、伝統的にかかと部分だけに「ソックシート」と呼ばれる革や布の中敷きを貼るデザインが多いんです。
つま先側は、靴本体のフットベッド(革や繊維ボードでできてる)に直接足裏が触れる、みたいな。履き込むうちに、このフットベッド自体が足の形に沈み込んで馴染んでいくんですね。
ドクターマーチンも、この伝統的なスタイルを採用して、あえてかかとから土踏まずまでの中敷きにしているモデルがある、っていうことなんですね。
手抜きどころか、むしろ「ちゃんとした作りの証」みたいな側面もあるのかも。
クッション性とサポートの役割

半分しかないって聞くと、「つま先側のクッション性、大丈夫?」って思いますけど、これもちゃんと計算されてるみたいです。
実は、私たちが歩くときって、一番衝撃がかかって疲れやすいのって、着地時に体重が乗る「土踏まずからかかとにかけての部分」らしいんです。
ドクターマーチンのハーフインソールは、まさにその大事な部分を重点的にサポートして、クッション性を確保する役割があるんですね。
「じゃあ、つま先側は?」ってなりますけど、前足部(踏み出す時)は比較的衝撃が少ないし、そこはもうドクターマーチン特有のあの「エアクッションソール(バウンシングソール)」が、しっかり仕事をしてくれるから大丈夫、っていう設計思想みたいです
。あのブニブニした独特のソールが、地面からの衝撃を吸収してくれるわけですね。
設計のポイント つまり、「衝撃を受けやすい後足部(かかと周り)はハーフインソールで保護し、前足部はソールのクッション性を活かす」という、役割分担がされているんですね。全部を厚くするんじゃなくて、必要なところにだけサポートを集中させる。すごく合理的だなと思います。
足先の余裕と通気性を確保

もう一つの大きな理由が、履き心地、特に「サイズ感」に関わる部分ですね。これが結構、私たちユーザーにとっては重要かも。
ドクターマーチンって、ご存知の通り、基本的にハーフサイズ(0.5cm刻み)の展開がないじゃないですか。
だから、サイズ選びが結構シビアだったりします。「UK7だとちょっとキツいけど、UK8だとちょっとユルい…」みたいなことが起こりがちです。
もし全面に厚い中敷きを敷いちゃうと、特に甲高さんや足幅が広い人は、つま先がギチギチに窮屈になっちゃう可能性がありますよね。指が曲がってしまったり、爪が当たって痛くなったり。
そこで、あえて前足部(つま先側)に中敷きを敷かないことで、足先に空間的な余裕(いわゆる「捨て寸」とは別の、縦方向の空間)を持たせてるんです。
これによって、足の指が当たりにくくなったり、指を動かせる自由度が上がって、結果的に靴擦れしにくくなるっていうメリットがあるみたいです。
確かに、ブーツって蒸れやすいですけど、つま先側に余計な布がない分、通気性アップや軽量化にもちょっとは貢献してるのかもしれないですね。
コスト削減ではない?品質との関係

「どうせコスト削減でしょ?」って思っちゃう気持ち、すごく分かります。私も最初はそう思いました(笑)。
でも、調べてみると面白いことがわかって。むしろ、高品質なモデルほどハーフインソールを採用しているっていう話もあるんです。
あるユーザーさんの声では、「半分しかないインソールのモデルの方が、中底(靴本体の底、フットベッドのことですね)が安いスポンジ素材じゃなくて、しっかりした革や繊維ボードで作られてることが多い。
結果的に質が高い」なんていう意見もありました。
つまり、ペラペラの全面インソールでごまかしている靴より、フットベッド自体がしっかり作られていて、ソックシート(半分中敷き)だけ貼ってあるモデルの方が、靴としての作りは本格的、という見方もできるわけですね。
もちろん、全てのモデルがそうとは言い切れないですけど、少なくとも「全面インソール=高級」「ハーフインソール=安物」っていう単純な話ではないみたいです。
ドクターマーチンの靴の構造や履き心地に合わせた結果、あの「半分」っていう形が選ばれてる、って考えるのが自然かなと思います。
ドクターマーチンの中敷きが半分でも快適に

理由がわかっても、「理屈は分かったけど、でも実際、履きにくいんだけど…」っていう悩みもありますよね。特にサイズ調整とか、かかとが痛い靴擦れ問題とか。ここからは、ハーフインソールと上手に付き合いながら、マーチンを快適に履きこなすための具体的な対処法や、インソール選びのポイントを紹介していきますね。

靴擦れや、かかとが痛い時の対処法

ドクターマーチンと靴擦れは、もうセットみたいなもの…って言われるくらい、最初は革が硬くて痛い思いをしがちですよね。
いわゆる「儀式」なんて言われたりもします(笑)。
特にハーフインソールだと、中敷きの「端っこ」の段差が足裏(土踏まずあたり)に当たって気になったり、かかとが痛いと感じる人もいるかも。
そんな時は、いくつかの対策を組み合わせるのがおすすめです。
厚手の靴下を履く
まずは基本中の基本ですね。メリノウールや厚手のコットンなど、クッション性のある靴下を履きましょう。
これは、かかとやアキレス腱を物理的に保護してくれるだけでなく、靴内部での足の滑りを抑える効果もあります。
薄い靴下だとハーフインソールの境目が足裏に当たる感じがするかもですが、厚手ソックスならそういう違和感もかなり和らぎますね。
ヒールグリップやパッドを貼る
これはかなり効果的です。靴のかかと内側(アキレス腱が当たる部分)にクッションパッド(ドラッグストアや100均でも売ってます)を貼って、物理的に隙間を埋めて擦れを防ぐ方法です。
足が靴の中でしっかり固定されるので、かかとの浮きがなくなり、靴擦れしにくくなりますよ。ドクターマーチン公式でも「ヒールグリップ」が出てますね。
インソールで足の位置を調整する
靴擦れの原因って、足が靴の中で沈み込んで、かかとが靴の縁(ふち)の硬い部分に変な角度で当たることだったりします。
そういう時は、あえて薄めの中敷き(フルインソール)を一枚追加して、足全体の位置を少し底上げすると、縁に当たる場所がズレて痛みがなくなることがあります。
シークレットインソールみたいに厚いものである必要はなくて、ほんの数ミリ持ち上げるだけでも効果がある場合がありますよ。
ただ、インソールを入れすぎると今度は全体が窮屈になって、甲や指が圧迫されて別の場所が痛くなる可能性もあるので、厚さは慎重に選んでくださいね。
履き慣らし(エイジング)を促進する
根本的な解決としては、やっぱりこれに尽きますね。靴自体を自分の足に馴染ませる(=履き慣らし)ことです。
厚手の靴下やパッドはあくまで「痛みを緩和する」対症療法ですが、履き慣らしは「痛みの原因(革の硬さ)」を解消する根本治療みたいなものです。
ドクターマーチンが「一生モノ」と言われるのは、この履き慣らしを経て、自分の足の形に完全にフィットした状態になってからかなと思います。
ただ、この「儀式」がなかなか大変なんですよね。具体的なステップとしては、こんな感じが王道かなと思います。
履き慣らしの王道ステップ
- まずは室内で: 新品の状態では、まず家の中で履いてみましょう。テレビを見ている間や、家事をしている間に1〜2時間履くだけでも違います。
- ご近所から: 次は「コンビニまで」「最寄りの駅まで」といった、ごく短距離・短時間の外出から試します。15分〜30分程度が目安ですね。痛くなったらすぐ帰れる距離、というのがポイントです。
- 徐々に時間を延ばす: 短距離で問題なさそうなら、次は「半日(3〜4時間)」「一日(丸一日)」と、徐々に履いている時間を延ばしていきます。
- 休ませる: 毎日連続で履くと、足のダメージも蓄積しますし、靴が吸った汗も乾きません。革にも足にも良くないので、履いたら1〜2日は休ませるようにしましょう。
そして、このプロセスをサポートするのが「革の柔軟化」です。
革が硬いから痛いわけなので、その革を柔らかくしてあげれば、馴染むスピードも速くなります。そこで効果的なのが、革を柔らかくする「デリケートクリーム」(水分を多く含んだ保湿クリーム)ですね。
ポイントは、靴の外側だけでなく、内側にも塗り込むことです。特に靴擦れが起きやすい、
- 履き口の縁(ふち)の部分
- かかとが当たる内側(ヒールカップ)
- タン(ベロ)の付け根や縁
これらの部分に、指でデリケートクリームを薄く擦り込むように塗ってあげると、革がしなやかになって足当たりがかなりマイルドになります。外側に塗るよりもダイレクトに効果を感じやすいかなと思います。
【注意】クリームの塗りすぎと「荒業」について
デリケートクリームも、塗りすぎるとシミやカビの原因になる可能性があるので、あくまで「薄く」が基本です。目立たないところで試してからにしてくださいね。
また、ネットで検索すると「履いたままお風呂に入る」「ドライヤーの熱風を当てる」といった荒業も見つかりますが、これらは私は絶対におすすめしません。
革に深刻なダメージを与えたり、変形・硬化させたりするリスクが非常に高いです。最悪の場合、靴の寿命を縮めてしまうので、焦らず王道の方法でゆっくり育てるのが一番確実ですよ。
履かない時はシューキーパー(シューツリー)を入れてシワを伸ばし、型崩れを防ぐことも、結果的に快適な履き心地を維持することに繋がります。
革靴のお手入れや履き慣らしは、靴擦れ防止に直結します。時間はかかりますが、しっかりケアしながら少しずつ自分の足に馴染ませていくプロセスも、ドクターマーチンの醍醐味(だいごみ)の一つかなと思います。
ドクターマーチンのサイズ調整方法

ハーフサイズがないマーチンは、サイズ調整が本当に悩ましいですよね。「UK8だとブカブカだけど、UK7だとつま先が当たる…」みたいな。この「ちょっと大きいな」って時にどうするかがポイントです。
ドクターマーチンの公式でも「中敷きや厚手の靴下で調整してください」って言ってるくらい、インソールでの調整は定番の方法です。
サイズが大きすぎる場合の調整
靴がブカブカで大きいと感じる場合は、新しいフルインソールを1枚追加するのが一番手っ取り早いですね。
元からハーフインソールが入っている場合は、その上から重ねることになります(外せる場合は外した方がベターですが、詳しくは後述します)。
純正のコンフォートインソールを入れたら指1本分の隙間がちょうど良くなった、なんて話もよく聞きます。
目安として、インソールの厚みで0.5cm〜1.0cmくらいはサイズ感を小さく(タイトに)できるかなと思います。
インソールだけでなく、甲が浮く感じがするなら「シュータン(ベロ)パッド」をタン裏に貼るのも有効ですよ。
サイズが小さすぎる(きつい)場合の調整
こっちはかなり難しいです…。基本的には「買うサイズを間違えた」ということになっちゃうので…。
できることとしては、もともと入ってるハーフインソールを(もし外せるなら)外して、ごくごく薄いレザーインソール(1mm厚とか)に入れ替えるか、最悪インソール無しで履くか、ですね。
ただ、それでも窮屈な場合は、革を伸ばす「ストレッチャー」を使うか、潔く手放すことを考えた方がいいかもしれません。
靴は「大は小を兼ねる」とは言いますが、調整にも限界があります。特に小さいサイズを無理に履くのは足の健康にも良くないので、購入時のフィッティングは本当に慎重に行ってくださいね。
元の中敷きは外すべき?

新しいフルインソールを入れたい時、この「元の半分の中敷き、どうする?」問題にぶつかります。上から重ねるのか、剥がして交換するのか。
結論から言うと、「無理に外す必要はないけど、外せるなら外して交換した方がスッキリする」って感じですね。
最近のモデル(特にアジア製)は、両面テープで軽く留まってるだけで、端からゆっくり引っ張るとペリッと簡単に剥がせるものが多いみたいです。
こういう場合は、キレイに剥がして新しいフルインソールと入れ替えるのがベストです。その方が段差もなくなり、スッキリしますからね。
でも、Made in England(イングランド製)のモデルや、古いもの、スチールトゥ(安全靴仕様)のモデルなんかだと、接着剤でガッチリ接着されてて、無理に剥がそうとすると中底(フットベッド)まで痛めちゃう危険もあります。
【剥がす時の裏ワザ(自己責任で!)】 どうしても剥がしたい時は、ドライヤーの温風で靴の中(かかと部分)を1分くらい温めると、接着剤が柔らかくなって剥がしやすくなるそうです。
これはショップの店員さんに聞いたっていう人もいる方法ですが、革を傷めるリスクもゼロではないので、試す場合はあくまで自己責任で、慎重にお願いしますね!
無理そうだな、と感じたら、諦めて元のハーフインソールの上から新しいインソールを重ねるのが安全です。
その場合は、重ねる分タイトになるので、できるだけ薄手のインソールを選ぶのがポイントですよ。
もしくは、最初からインソールを重ねる前提で、靴のサイズをワンサイズ上げておく、という買い方もありますね。
純正インソールの種類と特徴

やっぱり一番安心なのは、ドクターマーチンが出してる「純正インソール」ですよね。
当然ですが、靴の形(木型)にピッタリ合うように作られてますから。いくつか種類があるので、目的に合わせて選ぶといいかなと思います。
主なラインナップを表にまとめてみますね。
| インソール名 | 主な特徴 | おすすめな人 | サイズ感への影響 |
|---|---|---|---|
| クラシック インソール | 標準タイプ。薄手で程よいクッション性。 | 元のインソールが劣化した人。サイズ感を変えたくない人。 | 小(ほぼ無し) |
| コンフォート(ソフトウェア)インソール | クッション性重視。かかと部分が厚いジェルパッド。 | 長時間歩く人。足が疲れやすい人。サイズ調整したい人。 | 大(0.5サイズ程きつく感じる) |
| レザー インソール | 表面が天然レザー。通気穴あり。薄手。 | ムレが気になる人。清潔感を保ちたい人。革の感触が好きな人。 | 小〜中 |
| ウォームウェア インソール | 保温素材(ボアなど)。冬用。 | 冬場にブーツを履く人。足元の冷えが気になる人。 | 大(厚手) |
クラシック インソール
元から入ってる中敷き(ハーフじゃないモデルの場合)とほぼ同じ、標準タイプです。薄手でクッション性もそこそこ。
元の中敷きがボロボロになっちゃった時の交換用として最適ですね。サイズ感を大きく変えたくない人向けです。
コンフォート(ソフトウェア)インソール
クッション性重視、もしくはサイズ調整したいならこれですね。
かかと部分が厚くなっていて、衝撃をすごく吸収してくれる高機能タイプです。長時間歩く日とか、ディズニーランドに履いていく!みたいな時には威力を発揮するみたいですよ。
レビューでも「全然疲れなかった」って声をよく見ます。ただし、厚みがある分、実質ハーフサイズくらい靴が狭くなるので、サイズ調整目的でない場合はそこだけ注意ですね。
レザー インソール
表面が天然レザーで、通気穴がたくさん開いてるタイプです。
クッション性というよりは、ムレ対策や清潔さを保ちたい人向け。革が足の形に馴染んでいくのも楽しみの一つかも。サイズへの影響はコンフォートほどではないですが、多少タイトにはなります。
純正インソールは、公式ショップやABCマートさん、Amazonとかでも買えるので、手に入りやすいのも良いところですね。
市販インソール選びのポイント

もちろん、純正じゃなくても優秀なインソールはたくさんあります。100均ので十分っていう人もいますしね。選ぶポイントは「目的」かなと思います。
低反発クッションタイプ(疲労軽減)
マーチンはソール自体にクッションはあるものの、地面の硬さを感じることもあります。
「歩くと足裏(特に母指球あたり)が痛くなる」っていう人には、低反発ウレタン素材のインソールがおすすめです。
「衝撃吸収」って書いてあるやつですね。 驚くことに、「純正より100均の低反発インソールの方が快適」っていう愛用者さんもいるくらいなので、侮れないです。
まずは安価なもので試してみるのも全然アリだと思います。選ぶなら、薄手で弾力があるものがいいですね。
アーチサポートタイプ(安定性)
土踏まず(アーチ)をグッと支えてくれるタイプです。
立ち仕事が長い人や、偏平足ぎみの人、歩くとすぐ疲れる人には良いかも。「スーパーフィート」とか「シダス」みたいな専門ブランドが有名ですけど、5,000円前後とちょっとお値段は張りますね。
足の骨格を支えてくれるので「足の疲れ方が全然違う!」っていう人もいるので、足裏に悩み(足底筋膜炎とか)がある人は検討してみる価値ありです。
薄型の調整用ハーフインソール(微調整)
「全体に敷くほどじゃないけど、かかとが浮く」とか「つま先がちょっと余る」みたいな時は、部分的なインソールも便利です。
「つま先用クッション」とか「ヒールクッション」って名前で売ってますね。元のハーフインソールの上に、かかと用クッションを重ねて貼る、なんていう使い方もできます。
必要な場所にだけ足せるので、他の部分が窮屈にならないのがメリットです。
市販品を買うときは、必ず靴と同じサイズか、ちょっと大きめを選んで、自分でハサミでカットして合わせるのが基本です。
マーチンの靴はつま先が丸くて幅もあるので、元の中敷き(もしあれば)を型紙にして、それに合わせて微調整してみてくださいね。
結論:安心な公式サイトでの購入
ここまでインソールの話をしてきましたが、そもそも「このマーチン、本物かな?」って心配しながら履くのって、ちょっと残念ですよね。
ハーフインソールが偽物の特徴ではないとはいえ、最近は本当に精巧な偽物も出回っているみたいで…。
ステッチの粗さとか、ソールの刻印とか、見分けるポイントはいろいろあるんですけど、正直、素人目には難しいのも事実です。
だから、私がいつも思うのは、インソールの仕様がどうであれ、結局は「信頼できるお店」で買うのが一番安心だよね、ってことです。
特にドクターマーチンの公式サイトや、正規取扱店として認められている大手ショップ(ABCマートさんとかですね)で購入すれば、中敷きが半分だろうと全面だろうと、「これがこのモデルの正規品の仕様なんだな」って100%自信を持って履くことができます。
インソールで調整する手間や、本物か不安に思うストレスを考えたら、まずは「間違いなく本物である」っていう大前提をクリアすることが、精神衛生上も一番大事かなと思います。
価格が安すぎる並行輸入品や、フリマアプリでの個人間取引は、偽物のリスクもゼロではありません。
もちろん、良心的な出品者さんもたくさんいますが、購入の際は、その商品の出所や販売者の評価などを、ご自身の責任でしっかり確認することが大切ですね。
ドクターマーチンの中敷きが半分の疑問解決
さて、今回はドクターマーチンの中敷きが半分である理由や、それにまつわる悩みについてお話ししてきましたが、いかがでしたか。
「半分しかない!」という最初の驚きが、少しでも「なるほど」という納得に変わっていたら嬉しいです。
最後に、これまでのポイントを簡単におさらいしておきますね。
ドクターマーチンの中敷きが半分なのは…
- 偽物ではない: 正規品でも普通の仕様です。心配無用!
- 伝統的な構造: 本格的な靴作りの名残(なごり)である可能性が高いです。
- 機能的な理由: かかとを重点的にサポートし、つま先には余裕を持たせる設計です。
- 品質の問題ではない: むしろしっかりした作りのフットベッドを持つモデルでの採用例もあるようです。
悩みへの対処法は…
- 靴擦れ・痛み: 厚手の靴下、ヒールパッド、インソールでの位置調整、そして「履き慣らし」が有効です。
- サイズ調整: 「ちょっと大きい」はインソール追加で調整可能。「きつい」のは難しいので購入時に注意です。
- インソール選び: まずは純正品が安心。市販品なら「クッション性」「サポート性」「薄さ」など目的で選ぶと良いですね。
ドクターマーチンの中敷きが半分の仕様は、最初は驚くかもしれないですけど、ちゃんと理由があるんです。
そして、もしそれが自分の足に「ちょっと合わないな」と感じたら、インソールを活用して自分好みに「育てる」ことができるのも、マーチンの魅力の一つかなと思います。
インソール交換や追加は、一番手軽にできるカスタマイズです。
ぜひ、インソールとも上手く付き合って、あなただけの一足を快適に履きこなしてくださいね。楽しいマーチンライフを応援しています!

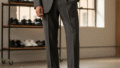
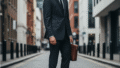
コメント